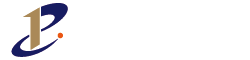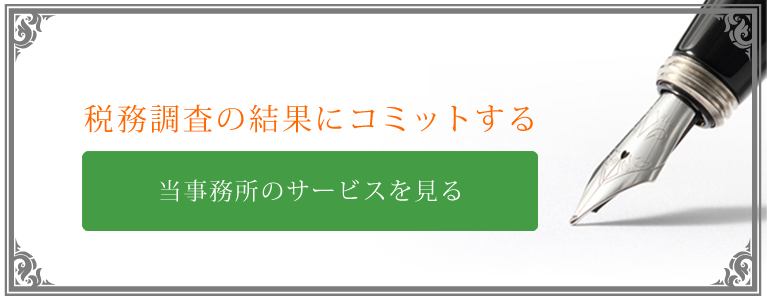2025/7/17|週刊文春に取材協力しました!
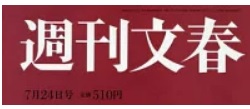
ZOZO前澤氏、養育費で4億円申告漏れの子育て事情
「少人数私募債スキームについて解説しました」
ネタバレになりますので詳細は割愛いたしますが、報道によりますと少人数私募債を利用した法人から個人への資産を低税率で移転するスキームを実施したようです。当局はスキームを放置してきた訳ではなく、税制改正で租税回避案件を牽制してきました。文春掲載記事とはリンクしませんが、改正の経過は次のとおりです。
○社債スキームへのパッチワーク(租税回避防止策)の変遷
当局はスキームを放置プレーしてきた訳ではない。イタチごっこの繰り返しだった。
・2013度税制改正
→「同族会社の株主や役員が支払いを受ける利子」については総合課税とした
・2014年度税制改正
→前出の改正で長期償還期間の社債発行などの改正逃れが散見された(というのは、2015年末までに発行された社債は従前のとおりメリットが享受可のため)ので、2016年以後に支払う社債利息についても総合課税を適用するとした
・2021年度税制改正
→社債発行会社とオーナーの間に別法人を介在させる改正逃れが散見されたが、法律の適用上、別法人を介在させたスキームは一応適法で放置されてきた。この改正では「そこで社債を発行する法人の株主が法人である場合、その法人の株を一定以上持つ個人についても総合課税にする」とした。
3度の税制改正、足掛け9年で封じ込めたことになる。ただし、株主や役員でない人が支払いを受ける社債利息は規制の対象ではないので、今も分離課税約20%が適用されます。ただ、実感としてはレアケースといえるでしょう。例えば、儲かること必至な案件で、ファンドのビークルの1つで発行する社債を第三者に社債を引き受けてもらう、なんてのは稀でしょうから。
順序が逆になりますが、そもそも「少人数私募債スキーム」をご存知のないかたへの解説をしておきます。
○社債スキームとは
所得税は累進税率なので、高所得者が節税するには、「総合課税(累進税率)」になる所得区分を避ける工夫が要ります。総合課税の所得区分は、不動産、給与、事業などがあり、総合課税の最高税率は45%、住民税の10%を合わせると55%となります。
具体的には総合課税でない所得区分である、「源泉分離課税)」が利用できるスキームを組むことになりますが、同族会社オーナーとしてはさらに、「法人税で損金となり、かつ、所得税で分離課税ができる」方法がベターです。
同族会社に社債を発行(少人数私募債)させ、オーナーが社債利息を得るスキームは、願ったり叶ったりのスキーム”だった”といえます。少人数私募債の社債利息の源泉税率は約20%。
このスキームは専門家の界隈では割と知られた手法で、実際にそれなりに利用もされてきました。同族会社からオーナー個人へ金銭が流れる場合の一般的な税金は、役員報酬(総合課税)や株主配当(総合課税)による所得課税がされ、前者は法人損金、後者は法人損金にならないという点が異なり、所得区分は総合課税に属します。
社債スキームは、多額の金銭を同族会社から個人に低い税負担で移転可能なもので、移転額は「社債利率の設定」に依存します。税効果は、10億円を年利10%で年1億円支払った場合、源泉分離課税後の手取り額は8千万円(源泉徴収約20%で税手続きは完結)となり、総合課税の55%と比べて年3,500万円手取り額が増えます。また、支払った同族会社側は、1億円の利益が圧縮できるので年3,500万円(法人実効税率を35%とする)が節税できます。社債元本はオーナーに償還されるので、結果、同族会社からオーナーへは「社債利息相当額」が低い税負担で移転できることになります。